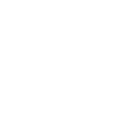- 手机扫一扫即可关注
- Scan your mobile phone to pay attention
- 安博官网首页登录入口
- 护佑生命 关爱健康
- 023-62925705
关于我们
安博官网首页登录入口是国资委直属央企中国医药集团所属企业国药控股股份有限公司下属二级子公司,2010年8月30日挂牌成立,坐落于重庆市南岸区茶园新区通江大道203号,注册资金3000万元。是一家集药品配送、医药物流、零售直销为一体的现代化综合性医药公司。
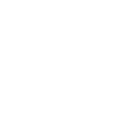
关于我们
安博官网首页登录入口是国资委直属央企中国医药集团所属企业国药控股股份有限公司下属二级子公司,2010年8月30日挂牌成立,坐落于重庆市南岸区茶园新区通江大道203号,注册资金3000万元。是一家集药品配送、医药物流、零售直销为一体的现代化综合性医药公司。